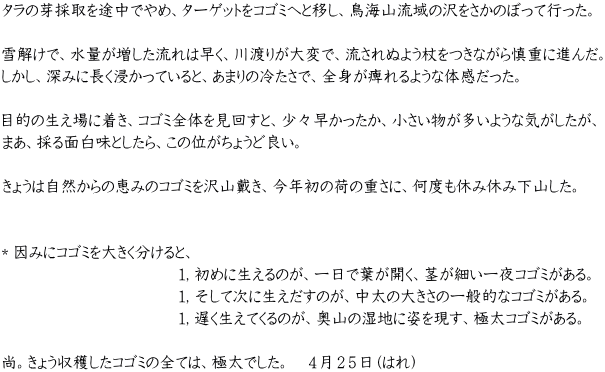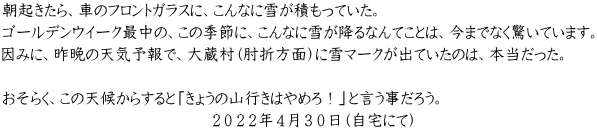コブシ
市内郊外から眺める「杢蔵山」風景(撮影時間5時14分)
愛車に雪が・・・
早めに生えてくれた細タケ(ネマガリタケ)
極太コゴミに手を伸ばし「ポキッ」と折る
久々のコゴミの大量収穫
薄明りの桜並木(撮影時間4時56分)
久しぶりの自然に、生き生きしていた
日向川沿いに咲くサクラは満開のようでした、
「鮭川」の水面に満月が・・・(撮影時間4時41分)
コゴミ(クサソテツ)↓
木の芽類の代表格、タラの芽摘みは忙し過ぎるが楽しい
久しぶりに渓谷を歩いた
きょうの収穫アイコ&タラの芽
群生するコゴミ(クサソテツ)
群がるアブラムシ
黒い毛虫
テントウムシのような虫
「最上川」の川脇に咲いていたソメイヨシノ
山ウドを数本
アイコ(ミヤマイラクサ)
山菜セット
スイセン
2022山菜採り2
2022山菜採り2
4/13
4/30
5/12
6/1
5/12
~当店「大自然」まるかじりやでは
採った物をその日に配送しております~
ご注文は、下記のメールか電話にてお願い致します
メールアドレスsehihide@yahoo.co.jp
「大自然まるかじりや」TEL0233(22)5645
山形県新庄市鉄砲町1-23
小野正敏
鳥海山の山容がくっきりと浮かび上がっていた
道沿いのサクラは満開でした
採り頃のタラの芽
4/13
6/1
4/30
11/20
4/14
2
5/1
5/14
5/14
11/20
4/14
5/1
2
この続きは3をクリックしてください






11.jpg)



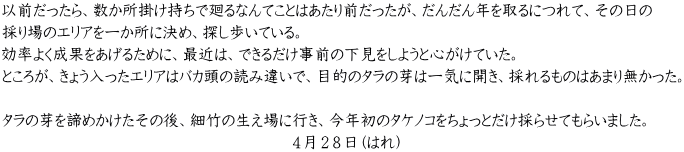









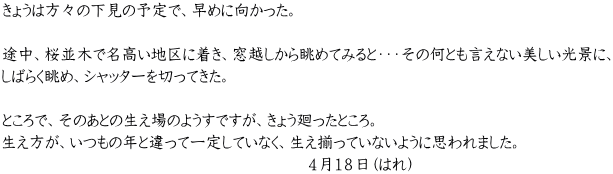






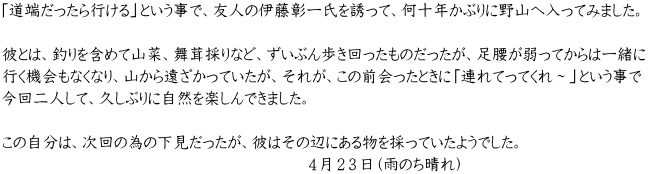
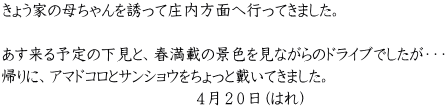






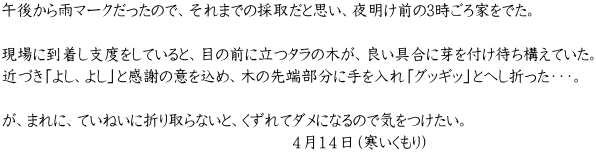
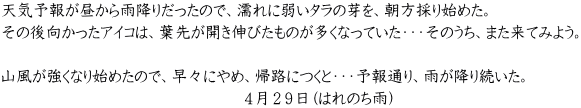

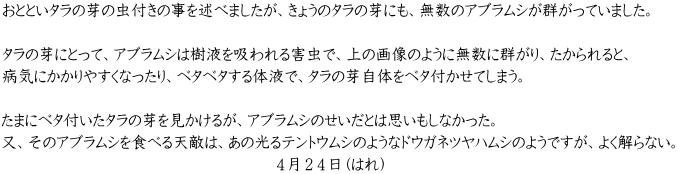


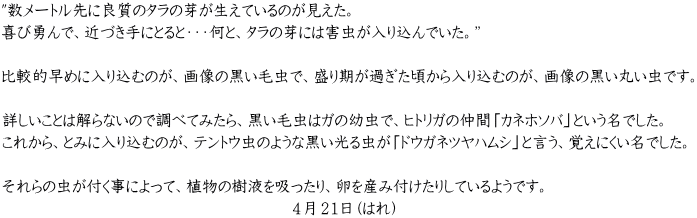




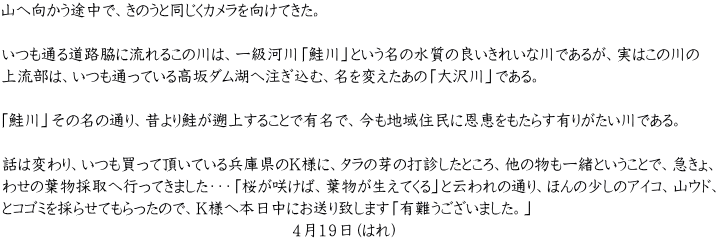


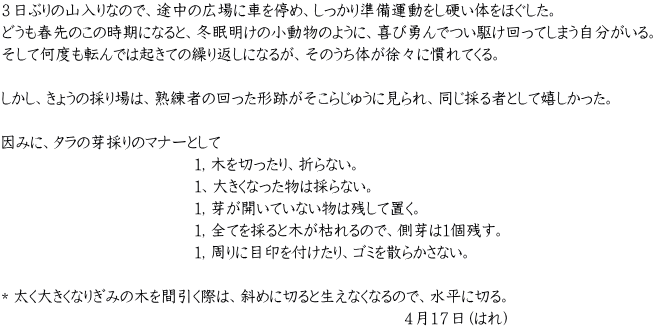
111.jpg)